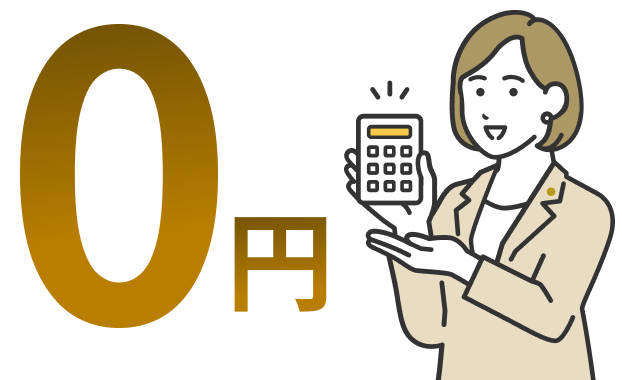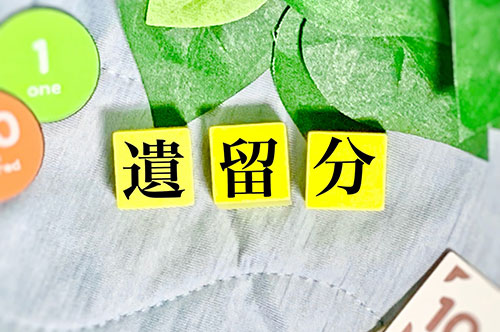胎児にも相続する権利がある|胎児が相続する場合の注意点とは?
- 遺産を受け取る方
- 相続
- 胎児

岩手県の令和4年における死亡者数は1万9342人で、前年の1万7631人よりも1711人も増加しています。この流れに伴い、相続の発生も増加傾向にあると推測されます。
子どもは民法が定めた法定相続人に含まれますが、胎児だった場合、相続権が認められるのでしょうか。
このコラムでは、胎児の相続権、相続割合、注意点などについて、ベリーベスト法律事務所 盛岡オフィスの弁護士が分かりやすく解説していきます。


1、胎児にも相続権が認められる
子どもが母親のお腹の中にいる段階で、父親がなくなったような場合、お腹の中の子どもも父親の権利を相続する権利を有しているのでしょうか。
ここでは、胎児の相続権について、民法の基本的なルールについて解説していきます。
-
(1)相続に関して胎児はすでに生まれたものとみなされる
民法では、胎児をすでに生まれたものとみなして、相続権を保障しています。つまり、胎児にも相続権が認められることになります。
胎児は近い将来に人として権利能力を持つことが予測されており、それにもかかわらず、相続権を持てないとするのでは、公平とはいえません。
このような不公平を解消するために、民法886条1項には、以下のように規定があるのです。第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
-
(2)胎児が死産だった場合は?
ただし、民法第886条2項には、「前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない」と規定されているため、胎児が生きて生まれなかった場合には相続権はありません。
-
(3)胎児が生まれてから死亡した場合は?
胎児が生まれた後、死亡した場合はどうなるのでしょうか。この場合、民法第886条1項の出生が擬制されることになるため、胎児にも相続権があることになります。
被相続人と妻、子ども、お腹の中の胎児がいる場合について具体的に考えてみましょう。・胎児が死産だった場合
胎児が死産だった場合には、相続権が認められません。そのため、相続人は妻と子の2人です。
・胎児が生まれてから死亡した場合
短い時間でも胎児が生きて生まれた場合には、相続人は妻と子と胎児の3人です。しかし、その後死亡しているため、相続分は母親が引き継ぐことになります。
2、胎児の相続割合は?
遺産全体に対して各相続人が有している権利の割合のことを「相続分」といいます。
ここでは、胎児の法定相続分(民法に定められた相続分)の割合についてケースごとに解説していきます。
-
(1)配偶者・胎児が相続人の場合
被相続人の配偶者と胎児の2人が相続人の場合、各相続人の相続割合はどれくらいなのでしょうか。
法定相続分は、以下の通りに規定されています(民法第900条1号)。- 配偶者の相続分は「2分の1」
- 胎児(子)の相続分は「2分の1」
胎児は、すでに生まれたものとみなされるため、配偶者と胎児の法定相続分はそれぞれ「2分の1」となります。
-
(2)配偶者・子ども1人・胎児1人が相続人の場合
今回のように、子どもが2人いる場合には、子全員についての総体的な相続分である「2分の1」を2人で均等に分けることになります。
したがって、各相続人の法定相続分については、以下の通りです。- 配偶者が「2分の1」
- 子どもが「4分の1」
- 胎児が「4分の1」
-
(3)離婚した元配偶者と胎児1人の場合
それでは、妻が夫の子を妊娠中に夫婦が離婚し、妊娠中に夫が死亡した場合の相続人や法定相続分はどうなるのでしょうか。
この場合、被相続人である夫が死亡すると、妻は夫の配偶者ではなくなるため、相続人にはあたりません。他方で、胎児については生まれたものとみなされるため、相続人となります。
したがって、相続人の配偶者がいない場合は、以下のようになります。- 第1順位の血族相続人(子)のみが相続人
3、胎児が相続する場合の注意点
胎児が相続権を有する場合には、相続手続きについてどのような点に注意すべきなのでしょうか。
ここでは、胎児が相続する場合の注意点について解説していきます。
-
(1)遺産分割協議は胎児の出生後に行う
まず、胎児が相続人である場合、遺産分割協議は胎児が生まれてから行うようにしましょう。なぜなら、胎児が生まれる前に遺産分割協議を行う場合、胎児の母親が代理して胎児の権利を行使できるかについては法的な争点となるおそれがあるからです。
前述の通り胎児にも相続権が認められていますが、これは、胎児の段階では権利能力を認めないものの「生きて生まれた場合には、権利を持つ存在だったとさかのぼって認める」というものです(出生の擬制(ぎせい))。
このような考え方によれば、胎児の段階では権利能力がないため、母親の代理による権利行為もありえません。もし、出生前に他の相続人らが遺産分割協議を行ったとしても、相続人の一部を除外した無効な遺産分割となるため、やり直しが必要になります。 -
(2)遺産分割をする場合には特別代理人の選任が必要
子どもが生まれた後は、遺産分割協議を行うことになりますが、生まれたばかりの子どもは当然自らの権利を行使することができません。
原則として、未成年者が法律行為を行う場合には、親権者が法定代理人となります。父母の一方が死亡した場合には、生存している親権者が単独で親権を行使することになります(民法第818条3項但書)。
しかし、親権者と子どもの利益が相反する場合、親権者が子を代理することはできず、特別代理人を選任しなければなりません(民法第826条1項)。特別代理人を選任するためには、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
相続人となる子どもが複数人いる場合には、それぞれの子どもに対して別の特別代理人を選任する必要があります。 -
(3)遺言があれば遺産分割は不要
被相続人が遺言書を残しておけば、遺産分割協議は不要となります。
遺言書によって、すべての財産の分け方を指定している場合、相続人が遺産分割協議を行う必要はありません。
ただし、遺言を作成する場合には、遺留分に注意する必要があります。遺留分とは、特定の法定相続人に認められている相続財産に対する最低限の取り分のことです。遺留分を侵害する形で遺言書を作成した場合には、のちのち相続トラブルに発展するリスクがあります。
4、胎児に相続させたい場合には、弁護士に相談すべき
胎児に遺産を承継させたい場合に、弁護士に相談すべき理由を解説していきます。
-
(1)子どもに確実に財産を相続するための遺言書を作成できる
弁護士に依頼することで、生まれてくる子どもに確実に財産を相続させるための遺言書を作成できます。遺言書によって希望どおりに相続を実現するためには、適切に遺言書を作成しなければなりません。相続人や相続財産・相続割合などが適切に指定できていないと、遺言として効力が生じないおそれもあります。
相続案件の実績がある弁護士に相談することで、適切な内容で遺言書が作成され、希望どおりに子どもに財産を残せるでしょう。 -
(2)弁護士であれば遺言執行者となれる
弁護士は、遺言執行者に指定することができます。
遺言執行者とは、遺言書どおりに相続を実現するために必要な事務を行う者のことです。遺言執行者は遺言書で指定することで選任することができます。
実績のある弁護士を遺言執行者に指定しておけば、遺言者が死亡した後に、スムーズに相続手続きを進めることができます。 -
(3)相続トラブルの際も適切な助言・サポートができる
相続トラブルが発生した場合にも、弁護士に適切な助言やサポートを求めることができます。
相続が開始した場合には、期限内に相続税の申告や、不動産の相続登記を行う必要があります。手続きが分からない場合でも、弁護士に依頼することで適切に対応してもらうことができます。
お問い合わせください。
5、まとめ
生まれる前の胎児にも相続権が与えられます。胎児であっても生きて生まれてきた場合には、相続する権利が認められることになります。
胎児に遺産を相続させたいという場合には、弁護士に相談したうえで、適切な遺言書を作成しておくことがポイントです。
これから生まれてくる子どもが、確実に遺産を相続できるようにしておきたいという場合は、相続案件の実績がある弁護士に相談することが重要です。ベリーベスト法律事務所 盛岡オフィスには相続問題の解決実績がある弁護士が在籍しております。お気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています