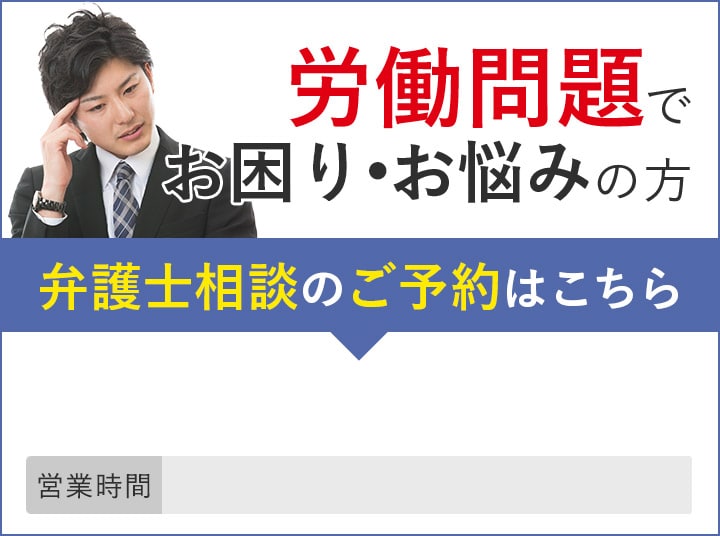懲戒解雇されたら給料はどうなる? 損害賠償分の相殺や相談先を解説
- 不当解雇・退職勧奨
- 懲戒解雇
- 給料

令和5年度に岩手県内の総合労働相談コーナーに寄せられた民事上の個別労働紛争相談は3822件で、そのうち懲戒処分に関するものは141件でした。懲戒解雇は重い処分であるため、全体数からすると比較的少ない件数ではありますが、一定の相談件数があることがわかります。
懲戒解雇されても、働いた分の給料は会社から受け取ることができます。そのため、会社が一方的に損害賠償分を給料から差し引くことは違法です。
本記事では、懲戒解雇されたら給料はどうなるのか、懲戒解雇された場合の相談先などを、ベリーベスト法律事務所 盛岡オフィスの弁護士が解説します。
出典:「令和5年度の個別労働紛争解決制度施行状況について」(岩手労働局)


1、懲戒解雇されたら、働いた分の給料はどうなる?
ここでは、懲戒解雇された場合における働いた分の給料の扱いや、無効な懲戒解雇における解雇後の給料について解説します。
-
(1)懲戒解雇されても、働いた分の給料は受け取れる
懲戒解雇されたとしても、それまでに働いた分の給料は受け取る権利があります。
使用者(会社)は労働者(従業員)に対して、労働時間に応じた給料(賃金)を支払わなければなりません。仮に懲戒解雇をしても、それまでの労働がなかったことにはならず、給料は発生します。
もし会社が懲戒解雇を理由に給料を払わない場合は、弁護士のサポートを受けながら会社に対して給料の支払いを請求しましょう。 -
(2)懲戒解雇が無効の場合は、解雇後も給料が発生する
労働者の行為の性質、態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められない懲戒解雇は無効です(労働契約法第15条)。
懲戒解雇が無効である場合、解雇後に職場を離れている期間についても、給料全額が発生します。解雇された労働者が働けなかったのは、不当解雇をした会社の責に帰すべき事由によるためです(民法第536条第2項)。
ただし、解雇後に別の会社で働いて収入を得ていた場合は、元の会社から支払われるべき解雇後の給料のうち4割を上限とする控除が認められています(最高裁平成18年3月28日判決)。
たとえば、解雇後の期間に対応する給料が100万円で、その期間に別の会社で働いて同額の100万円を受け取ったとします。
この場合、解雇された会社から受け取れる解雇後の給料は、4割が控除されて60万円となります。 -
(3)懲戒解雇時における解雇予告手当の取り扱い
懲戒解雇が有効だとしても、使用者は労働者に対し、原則として30日以上前に解雇予告をしなければなりません。
解雇予告をしない場合、または解雇の予告期間が30日未満である場合は、使用者は労働者に対し、以下の金額の解雇予告手当を支払う必要があります(労働基準法第20条)。- 解雇予告をしない場合:30日分以上の平均賃金相当額
- 解雇の予告期間が30日未満である場合:30日から予告期間分を短縮した日数分以上の平均賃金相当額
ただし、労働者の責に帰すべき事由に基づいて行われる解雇(懲戒解雇を含む)の場合は、労働基準監督署の認定を受けた場合に限り、解雇予告および解雇予告手当の支払いに関する義務が免除されます(労働基準法第20条第3項、第19条第2項)。
使用者が上記の認定を受けた場合は、解雇予告手当を請求できないのでご注意ください。 - 解雇予告をしない場合:30日分以上の平均賃金相当額
2、給料から損害賠償分を差し引くのは違法?
労働者が懲戒解雇されるような悪質な就業規則違反を犯した場合は、使用者に対して損害賠償責任を負うことがあります。
ただし、会社が一方的に給料から損害賠償を天引きするのは違法です。
-
(1)会社が一方的に給料から天引きするのは違法
労働基準法第24条第1項では、賃金(給料)の「全額払いの原則」が定められています。
使用者は原則として、労働者に対し、控除することなく給料の全額を支払わなければなりません。例外的に控除が認められているのは、以下のものに限られます。例外的に控除が認められているケース- 法令で控除が認められているもの(所得税、住民税、社会保険料など)
- 労使協定によって控除が認められているもの
懲戒解雇に伴う損害賠償は、上記の控除が認められているものに当たりません。
したがって、会社が一方的に給料から損害賠償を控除することは労働基準法違反に当たります。 -
(2)労働者の同意があれば天引きは有効|ただし、自由な意思による場合のみ
会社による一方的な損害賠償の天引きは違法ですが、労働者が相殺に同意した場合には、給料から損害賠償を天引きすることが認められる余地があります。
ただし、給料と損害賠償の相殺が認められるのは、労働者が自由な意思に基づいて相殺に同意したと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときに限られます(最高裁平成2年11月26日判決)。
たとえば、会社が労働者に圧力をかけて、給料と損害賠償の相殺についての同意を強要するようなケースも想定されます。
このような場合には、労働者の自由な意思による同意があったとは言えないため、給料と損害賠償の相殺は無効となる可能性が高いでしょう。
もし会社に、給料から損害賠償を天引きすることに同意するよう強要されたら、弁護士のサポートを受けながら天引きの無効を主張し、未払い分の速やかな支払いを求めましょう。
お問い合わせください。
3、懲戒解雇された場合の相談先
会社に懲戒解雇されたとしても、解雇をそのまま受け入れるべきではありません。
日本の解雇規制は厳しいため、懲戒解雇が無効と判断される可能性は十分あります。仮に解雇を受け入れるとしても、会社と交渉すれば退職金の支払いなどを引き出せるかもしれません。
理不尽と思われる理由で懲戒解雇されたときは、以下の窓口へ相談しましょう。
-
(1)総合労働相談コーナー|労働基準監督署、都道府県労働局
労働基準監督署や都道府県労働局には「総合労働相談コーナー」が設けられています。総合労働相談コーナーでは、専門の相談員に労働問題について幅広く相談できます。
解雇についても、総合労働相談コーナーで相談を受け付けています。解雇の無効を主張するための方法についてアドバイスを受けられるほか、都道府県労働局が設けている「個別労働紛争解決制度」の案内を受けることもできます。
総合労働相談コーナーは無料で利用できるので、突然懲戒解雇されて戸惑っている方は相談してみるとよいでしょう。 -
(2)労働組合
事業場の労働組合に所属している場合は、労働組合の窓口に相談することも有力な選択肢です。
労働組合は、労働者の権利を守ることを目的としています。所属する労働者が不当に懲戒解雇された場合には、使用者に対して抗議をしてもらえることがあります。
労働組合の大きな特徴は、使用者との団体交渉権が認められていることです。労働組合側からの団体交渉の申し入れを、使用者は正当な理由なく拒否することができません。
団体交渉を通じて不当解雇に関する抗議をしてもらえば、解雇の撤回やその他の合理的な解決につながる可能性があります。 -
(3)弁護士
会社に対して不当解雇を主張するに当たっては、法律の専門家である弁護士に相談するのが安心です。
弁護士は労働者の代理人として、懲戒解雇の経緯や法律上の規制を踏まえ、会社に対して不当解雇の無効を主張します。
弁護士が法的根拠に基づいて、解雇の無効を主張すれば、会社側が不利な立場にあることを悟り、何らかの和解案を提示してくることも期待できます。
不当解雇に関する争いが労働審判や訴訟に発展しても、弁護士に依頼していれば代理人としてそのまま対応を任せることが可能です。
弁護士に相談するメリットについては、次章でさらに詳しく解説します。
4、懲戒解雇されたことについて、弁護士に相談するメリット
懲戒解雇について相談できる窓口はいくつかありますが、その中でも弁護士に相談することには、主に以下のメリットがあります。
- 労働者の代理人として、迅速かつ適切に対応してもらえる
- 会社に対して直接不当解雇の無効を主張し、具体的な対応(解雇の撤回や解決金の支払いなど)を求めることができる
- 法的な根拠に基づいて、解雇の無効を説得的に主張できる
- 労働審判や訴訟に発展しても、戸惑うことなくスムーズに対応してもらえる
不当解雇に関するトラブルを適切な条件で解決するためには、弁護士に相談・依頼するのが安心です。
理不尽な理由で懲戒解雇されてしまったら、速やかに弁護士へご相談ください。
5、まとめ
懲戒解雇された場合でも、解雇日までの給料は受け取る権利があります。給料が振り込まれた際には、損害賠償などで勝手に天引きされていないかどうかを確認しましょう。
また、懲戒解雇自体が無効と判断されるケースも少なくありません。弁護士に相談して、懲戒解雇の無効を主張できるかどうか検討しましょう。
懲戒解雇の原因となった就業規則違反について、会社から損害賠償を請求された場合も、弁護士に相談することをおすすめします。
ベリーベスト法律事務所は、会社とのトラブルに関する労働者のご相談を随時受け付けております。会社に懲戒解雇されてしまった方は、適切な対処法を検討するため、お早めにベリーベスト法律事務所 盛岡オフィスの弁護士へご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています