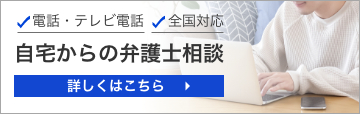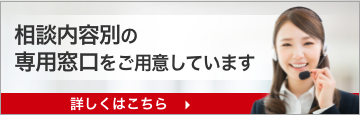無期転換ルールとは? 適用条件や企業側の注意点をわかりやすく解説
- 一般企業法務
- 無期転換ルール
- わかりやすく

2023年度に岩手県内の総合労働相談コーナーに寄せられた労働に関する相談は1万1564件でした。
雇用期間が5年を超える契約社員には、「無期転換ルール」に基づいて正社員に転じる権利が生じることがあります。
本記事では無期転換ルールについて、適用条件や企業側の注意点などをベリーベスト法律事務所 盛岡オフィスの弁護士が解説します。
1、無期転換ルールとは?
「無期転換ルール」とは、契約期間が5年を超える有期雇用労働者の申込みによって、有期労働契約を無期労働契約へと転換させることができる制度です(労働契約法第18条1項)。
-
(1)無期転換ルールの目的
無期転換ルールの目的は、有期雇用労働者の雇用継続に対する期待を保護し、その地位を安定させることです。
有期雇用労働者は、契約期間が満了するたびに雇用契約を打ち切られるリスクがあるため、不安定な地位に置かれています。
長年同じ職場に勤めていて、次も契約を更新してもらえるだろうと考えていたのに、突然雇い止めに遭って職を失うのは労働者にとって酷な面があります。
そのため、契約期間が5年を超える有期雇用労働者に対しては、雇用契約の無期転換を求める権利が認められています。 -
(2)無期転換ルールの適用条件
無期転換ルールが適用されるのは、以下の要件をいずれも満たす労働者です(労働契約法第18条第1項)。
① 有期労働契約の通算期間が5年を超えること
契約終了後、一定期間の後に再雇用された場合でも、空白期間が6か月未満であれば、前後の契約期間を通算することができます(同条第2項)。
② 有期労働契約が過去に1回以上更新されていること
上記の要件を満たす有期雇用労働者が、使用者に対して無期転換の申込みを行った場合、有期労働契約の期間満了日の翌日から自動的に無期労働契約へと転換されます。
使用者はこの場合、無期転換の申込みを拒否することができません。 -
(3)2024年4月施行|無期転換ルールに関する事項の明示義務付け
2024年4月1日から施行された改正労働基準法施行規則により、使用者が有期雇用労働者を雇い入れる際には、以下の事項を明示することが新たに義務付けられました(労働基準法施行規則第5条第1項第1号の2、第5項、第6項)。
- (a)有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限
- (b)無期転換の申込みに関する事項および無期転換後の労働条件
雇入れ時における上記の事項の明示が義務付けられたことには、有期雇用労働者の無期転換ルールに関する認知と理解を促す目的があります。
2、契約社員を無期転換する企業側のメリット・デメリット
契約社員などの有期雇用労働者を、無期転換によって正社員とすることには、企業側にとってメリットとデメリットの両面があります。
-
(1)契約社員を無期転換するメリット
有期雇用労働者を無期転換によって正社員とすることの主なメリットは、以下のとおりです。
- 長期的な視点で人材を育成できる
- 労働力を安定して確保できる
- 正社員登用制度が好感されて、企業のイメージアップに繋がる
-
(2)契約社員を無期転換するデメリット
その一方で、有期雇用労働者を無期転換によって正社員とすることには、以下のようなデメリットがあります。
- 人件費が増加する
- 雇用契約を打ち切ることが難しくなる
- 正社員登用制度の整備にコストがかかる
3、無期転換ルールについて企業が注意すべきこと
無期転換ルールについて、企業が労務管理上注意すべきポイントを解説します。
-
(1)無期転換ルールを踏まえた雇用管理の見直し
有期雇用労働者については、無期転換ルールの内容を踏まえて雇用管理を行うべきです。
具体的には、契約期間が5年に達する前の段階で、有期雇用労働者の雇用継続の可否について検討する機会を設ける必要があります。
たとえば、契約期間が2年の有期雇用労働者については、2回目の契約更新をすると、3期目の途中で無期転換ルールの対象になります。正社員として登用するつもりがないのであれば、3期目に入らずに雇い止めを検討すべきでしょう。
契約期間が3年の有期雇用労働者については、1回でも契約を更新すると、2期目の途中で無期転換ルールの対象になります。正社員として登用するつもりがないのであれば、2期目に入らずに雇い止めをしなければなりません。
このように、無期転換ルールの対象となる時期を正確に把握したうえで有期雇用労働者の契約期間を管理し、雇い止めするかどうかを適切に判断しましょう。 -
(2)労働条件の明示事項の再確認|無期転換ルールについて確実に明示
無期転換ルールに関する事項は、2024年4月1日から雇入れ時に明示すべき労働条件に追加されています。
労働条件明示義務違反は刑事罰の対象とされているほか(労働基準法第120条第1号、121条)、労使トラブルの原因にもなり得ます。
法令改正前から労働条件通知書の様式をそのまま使っている場合は、現行規定に合わせて速やかにアップデートを行いましょう。 -
(3)再雇用の従業員にも、原則として無期転換ルールが適用される
定年後に再雇用した従業員(嘱託社員など)についても、再雇用後の契約期間が5年を経過すると、原則として無期転換ルールが適用されます。
高齢の従業員に無期転換権を行使されると、不本意に雇用を継続せざるを得なくなってしまいます。定年後に再雇用した従業員については、雇用期間の管理をいっそう慎重に行いましょう。
なお、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」(有期雇用特別措置法)に基づく第二種計画の認定を受けた場合には、定年後に再雇用した従業員について、無期転換ルールの適用が免除されます(同法第8条第2項)。
第二種計画の認定は、適切な雇用管理に関する計画が作成されているかどうかを審査した上で、都道府県労働局長が行います。 -
(4)無期転換を回避するための雇止めは違法となるケースがある
無期転換ルールの適用を回避するため、契約期間が5年に達する前に雇い止めをしたとしても、「雇い止め法理」によって無効となることがある点に注意が必要です。
雇い止め法理とは、有期雇用労働者の雇用継続に対する合理的な期待を保護するための制度です(労働契約法第19条)。
以下の①~③の要件をすべて満たす場合には、有期労働契約が更新されたものとみなされ、雇い止めが無効となってしまいます。① 以下のいずれかに該当すること
- (a)有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあり、雇い止めが解雇と社会通念上同視できること
- (b)有期労働契約の更新に対する労働者の期待に合理的な理由があること
② 労働者が使用者に対して、契約期間の満了日までに契約の更新の申込み、または契約期間の満了後遅滞なく契約締結の申込みをしたこと
③ 使用者が申込みを拒絶することが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められないこと
労働者が恒常的な業務に従事している、契約が複数回更新されている、雇用の通算期間が長期にわたる、契約更新手続が形骸化している、労働者に対して継続雇用を期待させるような説明をした場合などには、雇い止め法理が適用される可能性が高くなります。
弁護士に相談して、雇い止めが無効となるリスクの程度や対処法などについてアドバイスを受けましょう。
4、無期転換ルールへの対応などを弁護士に相談するメリット
無期転換ルールへの対応など、人事・労務管理に関する問題については弁護士に相談するのが安心です。
弁護士は、労働契約法その他の法令を踏まえて、労使トラブルの予防に繋がる適切な人事・労務管理の方法をアドバイスいたします。
就業規則や雇用契約書を作成する際にも、弁護士にご相談いただければ丁寧にリーガルチェックを行います。
顧問契約を締結すれば、人事・労務管理やその他の法律問題について、いつでも弁護士へのご相談が可能です。労務コンプライアンスの強化を図りたい企業は、顧問弁護士との契約をご検討ください。
お問い合わせください。
5、まとめ
無期転換ルールは、有期労働契約が更新されて通算契約期間が5年を超える場合、労働者に無期転換申込権が発生するルールです。
使用者としては、有期雇用労働者を正社員として登用することのメリット・デメリットを踏まえた上で、社内制度の整備や無期転換ルールへの対応を適切に行うことが重要になります。
弁護士のアドバイスを受けながら、労務コンプライアンスの強化と労使トラブルの予防を図りましょう。
ベリーベスト法律事務所は、人事・労務管理に関する企業のご相談を随時受け付けております。クライアント企業のニーズに応じて、リーズナブルな料金からご利用いただける顧問弁護士サービスもご用意がございます。
無期転換ルールへの対応など人事・労務管理にお悩みの企業や、顧問弁護士との契約をご検討中の企業は、ぜひベリーベスト法律事務所 盛岡オフィスへご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています