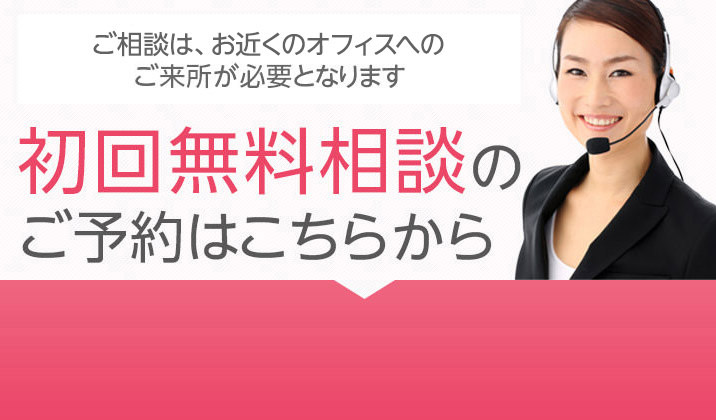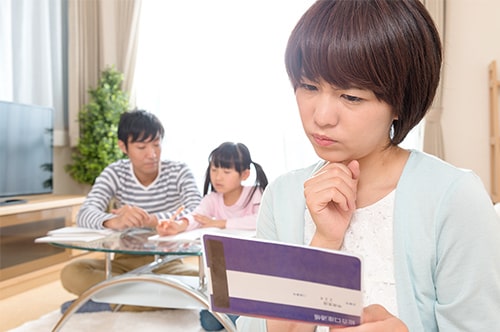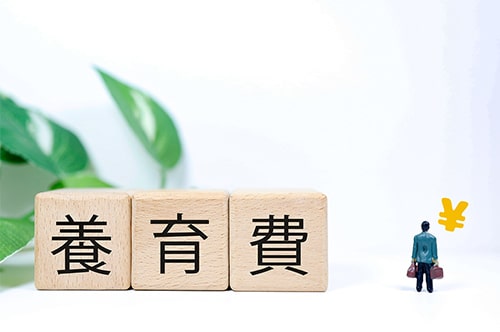離婚後に二度と相手と顔を合わせない方法はある? 合理的な対処法
- 離婚
- 離婚
- 二度と会わない

離婚後、「二度と相手と会いたくない」と考える方は少なくないでしょう。ただ、中には、離婚に際して決めることが決まらず連絡を取らなければいけない、子どもとの面会交流に付き添わなければいけない、勝手に相手が会いに来るといった事情から、相手と顔を合わせなければならない方もいらっしゃると思います。
しかし、強制的に相手と「二度と会わない」「接触しない」ためには、接近禁止命令などの法的手続きを申立てなければなりません。また、子どもがいる場合には、原則として面会交流が必要になります。
今回は、離婚後に相手と顔を合わせなくて済む方法・対処法などについて、ベリーベスト法律事務所 盛岡オフィスの弁護士が解説します。


1、離婚後は顔を合わせないようにできる?
離婚後に元配偶者と二度と会わないようにすることはできるのでしょうか。
-
(1)暴力や脅迫があれば接近禁止命令を申し立てる
配偶者から身体的な暴力や生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対する脅迫を受けた場合、裁判所に接近禁止命令の申立てをし、発令を受けることで、相手からの接触を避けることができます。もし、暴力や脅迫を受けた場合には、すぐ迷わずに警察へ相談しましょう。
相手が接近禁止命令に違反して接触をしてきた場合、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金が科されます。
このような接近禁止命令は、離婚後であっても申立てをすることが可能です。婚姻中に暴力や脅迫を受けていたという事情があれば、元配偶者も接近禁止命令の対象になりますので、接近禁止命令を利用してみるとよいでしょう。 -
(2)接触を避ける実践的な方法
配偶者からの暴力や脅迫がなければ、接近禁止命令を利用することはできません。
しかし、少しの工夫で、以下のような方法で相手と顔を合わせることを避けることができます。① 相手との連絡はメールやLINEで行う
子どもがいる場合、子どもとの面会交流や養育費などで相手と連絡をしなければならないことがあります。このような場合には、メールやLINEなどで直接相手と顔を合わせない方法で連絡をすることで、相手との接触を回避することができます。
② 親など第三者を介して連絡をする
相手とメールやLINEなどで連絡することも嫌だという場合には、親や友人、知人などの第三者を介して連絡をするという方法もあります。相手と顔を合わせたくない事情を説明すれば協力してくれる可能性はあるでしょう。
③ 離婚条件などを具体的に取り決めて接触の機会を減らす
離婚時に離婚条件の取り決めが曖昧だと、連絡する必要に迫られることがあります。離婚条件を定める際には、できる限り具体的に定めておき、離婚後のやり取りを最小限に抑えるようにしましょう。
なお、離婚時の取り決めを公正証書にし、必要な条項を入れておけば、養育費の未払いがあったとしても相手に連絡することなく、直ちに強制執行を申し立てて相手の財産を差し押さえることができます。
④ 遠方に引っ越して物理的に接触困難な状態にする
相手と二度と会わないようにするには、遠方に引っ越して物理的に接触困難な状態にすることもひとつの方法です。
ただし、子どもがいる場合、遠方の引っ越しは生活環境に大きな変化を生じさせ、子どもにとってストレスになる可能性があります。引っ越しをする際には、子どもの年齢や意向なども踏まえて慎重に検討することをおすすめします。
2、離婚時に決めておくべき重要事項
離婚時に決めておくべき重要な事項としては、以下の項目が挙げられます。
-
(1)親権
夫婦に子どもがいる場合、子どもの親権者をどちらかに指定しなければ離婚は認められません。
親権者に指定された親が、子どもと一緒に生活する「監護親」になるのが基本です。子どもにとっていい環境を提供できるのはどちらかを考えて、話し合っていきましょう。 -
(2)養育費
親権者として子どもと一緒に生活する監護親は、一方の親に対して、養育費を請求することができます。
養育費の金額は、基本的には夫婦の話し合いで決めることになりますが、金額を決める際には、裁判所が公表している養育費算定表を参考にするとスムーズに取り決めができます。
養育費算定表を使えば、子どもの年齢・人数と夫婦の収入によって養育費の相場を簡単に計算できます。 -
(3)慰謝料
配偶者にDV、モラハラ、不倫などの行為があった場合には、慰謝料を請求することができます。
ただし、慰謝料を請求する際には、違法な行為があったことを裏付ける証拠が必要になります。離婚を伝える前にしっかりと証拠を集めることをおすすめします。 -
(4)財産分与
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた共有財産を離婚時に清算する制度です。
夫婦の財産形成に対する貢献度は、基本的には等しいと考えられていますので、原則として2分の1の割合で財産分与を求めることができます。
適正な財産分与を行うには、お互いの財産をすべて明らかにする必要がありますので、相手が財産を隠している疑いがあるときはしっかりと調査してから財産分与を行うようにしてください。 -
(5)面会交流
面会交流とは、子どもと離れて暮らす親が子どもと定期的・継続的に交流することをいいます。
離婚して二度と顔を合わせたくないと思っていても子どもがいる場合には、面会交流を実施するよう裁判所から求められることが多いです。離婚の話し合いの際には、面会交流の方法や条件などを取り決めておくようにしてください。
お問い合わせください。
3、面会交流は必須?
面会交流は必ず行わなければならないものなのでしょうか。
-
(1)子どもがいるなら原則として面会交流を実施すべき
離婚をすると相手に二度と会いたくないという思いから、相手と子どもとの面会交流を拒否してしまう方もいます。
しかし、面会交流は、子どもが親との交流を通じて、親からの愛情を確認しつつ健全な育成を実現することを目的とした制度です。そのため、親の個人的な事情で親と子どもとの面会交流を制限することはできません。
なお、子どもが「会いたくない」と言うこともあるかもしれませんが、本心からの発言ではなく、親の気持ちを汲んで発言している可能性もあります。そのため、なぜそのように思うのかを尋ねるなど、子どもの心情に配慮した対応が必要になります。 -
(2)相手に会わなくても面会交流は可能
面会交流は、親と子どもが会うのが目的ですので、必ずしも親同士が会う必要はありません。
子どもが一人で面会できるような年齢であれば、送り迎えだけあなたがしてあげれば、面会交流に立ち会う必要はなく、相手に会わなくても面会交流を行うことができます。
また、あなたの両親の協力が得られるようであれば、子どもの受け渡しや立ち会いをあなたの両親に頼むことで、あなた自身は相手とかかわらずに面会交流を行うこともできます。
このように相手に会わなくても面会交流は可能ですので、相手に二度と会いたくないというのは面会交流を拒否する理由にはなりません。
4、弁護士などの専門家を頼った解決策
相手に二度と会いたくないという場合には、弁護士などの専門家を頼ることも有効な解決策となります。
-
(1)相手と顔を合わせないための対策をアドバイスできる
離婚後に相手と顔を合わせたくないという場合には、弁護士に相談することで相手と顔を合わせないための対策やアドバイスを受けることができます。
具体的な状況によっては、接見禁止命令の申立てなどの法的手段により希望を実現できる可能性もありますので、離婚準備に入った段階で弁護士に相談するようにしましょう。
早期に弁護士に相談することで、さまざまな対策を講じることができます。 -
(2)離婚時も弁護士が代理人として対応することで相手に会わずに離婚できる
離婚後に相手と顔を合わせたくないという方は、離婚時の相手との話し合いも苦痛に感じるはずです。
弁護士に依頼して代理人として相手との交渉を任せることも可能です。精神的ストレスを大幅に軽減できますので、相手の顔を見たくないという場合は弁護士への依頼を検討してみましょう。 -
(3)親子交流支援団体を利用することで相手と会わずに面会交流を実施できる
面会交流の際に相手と会いたくないという場合には、親子交流支援団体を利用することも有効な対策といえます。
親子交流支援団体とは、父母間の連絡調整、子の受け渡し支援、見守り支援などさまざまな支援を行う民間の団体です。このような団体を利用すれば、二度と顔を合わせたくないという希望をかなえられるでしょう。
なお、弁護士に相談すれば親子交流支援団体の利用のアドバイスやサポートを受けることもできます。
5、まとめ
離婚をすると相手とは二度と会いたくない、顔を合わせたくないと考える方もいるでしょう。子どもの面会交流は必要ですが、最低限の連絡をとったり、支援団体を頼ったりすることで、相手と直接会うことを回避することは可能です。
さまざまな対策を講じることで相手と顔を合わせずに過ごすことは可能です。離婚の前段階から、相手との接触をなるべくとらずに進めたいという方も、まずはベリーベスト法律事務所 盛岡オフィスまでご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています