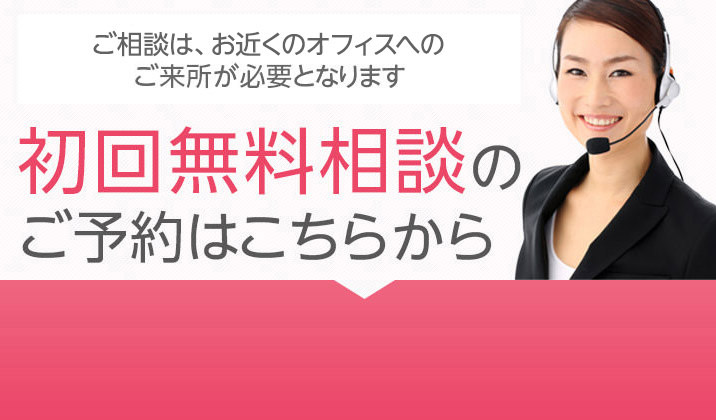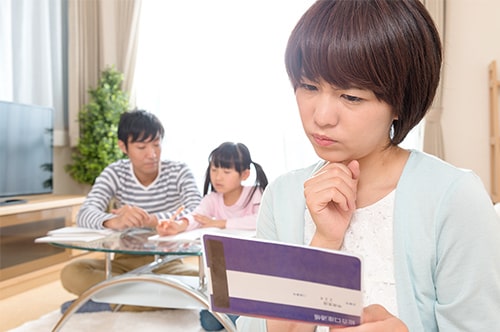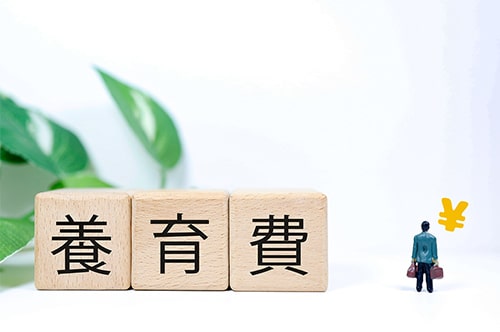離婚の誓約書を自作しても効力はある? 記載内容や注意点を解説
- 離婚
- 離婚
- 誓約書
- 自作
- 効力
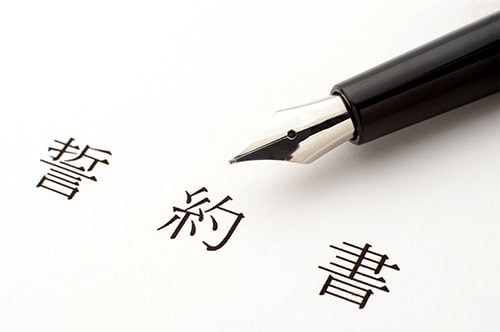
盛岡市の公表している盛岡市統計書によると、令和4年に盛岡市では600組の夫婦の離婚が成立しました。
協議離婚に伴い合意した離婚条件(離婚契約)については、あとのトラブルに備えて書面に残しておくことが大切です。ただ、書面を作成する際に、自作の書面(誓約書や離婚協議書)の効力に不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。
本コラムでは、自作の誓約書に効力があるのかどうか、誓約書にどのような内容を記載すべきかどうかについて、ベリーベスト法律事務所 盛岡オフィスの弁護士が解説していきます。


1、離婚の誓約書を自作した際の効力は?
そもそも誓約書とは、一方の当事者がもう一方の当事者に対して、将来に向けて何か約束をするときに作成する書類です。たとえば、不倫をした配偶者との婚姻生活を続ける際に「もう二度と不倫をしません。また不貞行為をしたら、離婚に合意します」といった内容を記載した書面が挙げられます。
協議離婚をするために、離婚条件についての合意内容を書面にすることもあるでしょう。この場合の書面は誓約書とは呼ばず、「離婚協議書」といいます。
離婚協議書は自作もできますが、公正証書(3章で詳しく解説)よりも効力は劣り、執行力はありません。たとえば、義務者が、養育費や慰謝料のような金銭の支払い義務を怠ったとしましょう。このとき、自作の離婚協議書があったとしても、支払い義務者の財産をすぐに差し押さえる、といったことはできません。
しかし、当事者双方の署名があれば、その離婚協議書は契約書と同じ効力を持ちます。したがって、離婚後に合意内容についての食い違いが生じても、自分の主張が正しいことを証明する証拠として役に立つでしょう。
2、離婚協議書に記載すべき内容
離婚協議書に記載すべき主な内容は、以下のとおりです。
それぞれの項目について詳しくみていきましょう。
-
(1)親権や養育費、面会交流
子どもがいる場合は、親権、養育費、面会交流について記載します。
親権とは、未成年の子どもの財産管理や、監護教育をする権利義務のことです。令和8年からは共同親権が選択できるようになりますが、現行法では、離婚後の共同親権が認められていません。現状、離婚後は「単独親権」となりますので、夫婦のどちらかを親権者に定める必要があります。
したがって、離婚協議書には「親権者がどちらになるのか」について、必ず記載しましょう。親権者と監護権者(子どもと一緒に住んで監護する人)が異なる場合は、監護権者についても記載しなければなりません。
また、経済的・社会的に自立していない子ども(未成熟子)の必要な経済的支援である養育費については、以下の内容を記載する必要があります。- 養育費の金額
- 支払い期間
- 支払日
- 支払い方法
- 学や病気、入院などで費用が必要になった場合に別途協議する旨
面会交流(離婚後に非親権者と子どもが交流すること)については、以下の内容を記載しましょう。
- 面会交流の頻度
- 面会交流の方法(直接会う、電話、手紙など)
- 面会交流の場所
- 宿泊を伴う面会交流の可否
- 親権者や第三者の立ち会いの有無
- 学校行事(入学式や運動会など)やイベントへの参加の可否
-
(2)財産分与
婚姻期間中に築いた財産(共有財産)を離婚時に分ける財産分与については、以下の内容を記載します。
- 誰から誰に対して何を分与するのか
- 支払い期限
- 支払い方法
- 振込手数料をどちらが負担するか
財産分与の対象となる財産は、預貯金、不動産、家具家電、車、退職金などです。
たとえば、車についての財産分与を行うとしましょう。車を夫が所有することになった場合は「評価額の半額を、妻に対して何年何月何日までに支払う」といった内容を記載します。 -
(3)慰謝料
離婚に際して慰謝料の支払いがある場合は、以下の内容を記載しましょう。
- 誰が誰に対して支払うのか
- 謝料金額
- 支払い期限
- 支払い方法
- 支払いが滞った場合の対応
-
(4)年金分割
年金分割とは、婚姻期間中の年金保険料納付額に対応する厚生年金記録を、離婚時に分割する制度です。離婚協議書には、「誰から誰に対する分与なのか」と「分割割合」を記載します。
なお、離婚協議書に記載しただけでは、実際の年金分割の手続きはできません。手続きをするには、離婚後に2人で年金事務所や年金相談センターへ行き、年金分割請求手続きをする必要があることに留意しておきましょう。 -
(5)清算条項
精算条項とは、離婚協議書に定めたこと以外に債権債務がないことを確認して、離婚後にお互い何ら請求しない約束のことです。清算条項を記載することで、離婚後にトラブルの蒸し返しを防ぐことができます。
一方で、デメリットもあります。たとえば、離婚協議のときに忘れていた夫婦間のお金の貸し借りを、離婚後に思い出して請求しようとしても、離婚協議書に清算条項がある場合は請求が認められません。
そのため、清算条項を入れる際には、請求し忘れている金銭債務がないかどうか、きちんと確認したうえで記載するようにしましょう。 -
(6)離婚届
離婚協議書には、離婚届について記載することも大切です。夫婦のどちらがいつまでに、どの市町村役場に離婚届を提出するのか記載しておきましょう。
3、離婚協議書は公正証書での作成がおすすめ
離婚協議書は「公正証書」で作成することにより、執行力を持たせられるメリットがあります。こちらでは、公正証書の概要と、公正証書を作成する場合の注意点を解説していきます。
-
(1)公正証書とは何か
公正証書は、紛争を予防するため法務大臣から任命された「公証人」に作成してもらう公文書(行政機関による正式な書類)です。私文書(個人が作成した書類)である離婚協議書に対して、執行力を持たせることができるのが、公正証書の特徴です。
執行力とは、債務者が契約通りに債務を履行しなかったときに強制執行(強制的に財産を回収する手続き)できる効力を指します。たとえば、元配偶者が養育費や慰謝料を取り決めのとおりに支払わなかったとしましょう。このとき執行力のある文書があれば、裁判を経ずに強制執行の手続きができます。元配偶者の給料・預貯金などを差し押さえて、未払い分を回収することが可能です。
ただし、公正証書に執行力を持たせるには、「強制執行認諾文言」を付ける必要があります。
養育費や慰謝料など、金銭の取り決めをする際に「支払いが滞ったら直ちに強制執行を受けることに合意する」といった文言を入れて、公正証書を作成するようにしましょう。 -
(2)公正証書作成時の注意点は?
先述のとおり、離婚協議書に金銭の取り決めを入れる際は、公正証書で作成することを検討しましょう。
特に養育費や慰謝料を分割で受け取ることになっている場合、途中で支払われなくなる可能性もあります。しかし、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成していれば、支払い請求のために裁判を起こす時間や費用、労力や精神的負担を軽減することが可能です。
また、公正証書の作成タイミングは、離婚届を提出する前をおすすめします。
離婚届の提出後でも、公正証書は作成可能ですが、離婚が成立してから作成しようとすると「もう離婚は成立したから」などと言って、元配偶者から非協力的な態度を取られる可能性があるため、注意しましょう。
4、離婚で悩んでいる方は弁護士に相談を
離婚協議書の書き方など、離婚のことでお悩みの方は、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士であれば、離婚協議書の内容を法的な観点から確認することが可能です。また、離婚条件に問題がないかどうか、慰謝料請求のための証拠の集め方など、納得して離婚するためのサポートができます。
自分ひとりで対応しようとすると、配偶者が逆上する、話し合いに非協力的になるなど、トラブルが起こることもあるでしょう。弁護士は交渉を代行することが可能なので、話し合いを円滑に進やすくなります。
また、弁護士に交渉を任せることで精神的なストレスを軽減できるほか、離婚条件でもめている場合は納得いく条件で離婚できる可能性が高まります。
離婚に関するお悩みがある方は、まず弁護士に相談してみてください。
お問い合わせください。
5、まとめ
離婚協議書は、自作であっても、当事者双方の署名があれば契約書と同じ効力を持
ちます。そのため、離婚条件について離婚後に食い違いが起きても、自分の主張を裏付ける証拠として有効です。
ただし、強制執行の内容を追加したい場合は、公正証書の作成を検討したほうがよいでしょう。
離婚協議書や離婚公正証書の作成でお悩みの方、離婚の進め方にお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 盛岡オフィスの弁護士にお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています